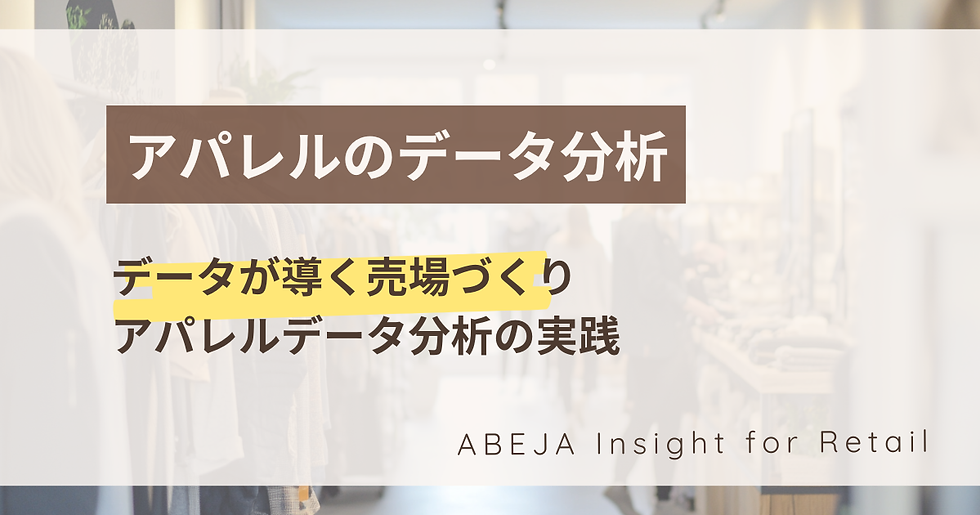
アパレルの店舗運営では、VMDや接客といった“感性の領域”が成果を左右すると言われてきました。しかし、顧客行動や購買動機が多様化する今、感覚だけでは売場を最適化できない時代が訪れています。
この課題を解決する手段として注目されているのが、データ分析を軸にした店舗運営。情報収集・来店・滞留・購買といった、売上に至る一連のファネルをデータ分析することで、「なぜ売れるのか」「どこに課題があるのか」を可視化し、改善を加速させることが可能になります。
この記事では、アパレルデータ分析の実践をテーマに、データを分析するうえで経るべきステップと、具体的な分析例について紹介します。
なお、以下の記事では、店舗DX・リテールDXについても解説しています。DXいついて理解を深めたい方は、併せて参考にしてみてください。
アパレル業界におけるデータ活用の必要性
変化する購買行動への対応
SNSやECの普及により、来店前の情報収集やブランド接触の形が多様化しています。顧客の意思決定は、オンライン上の情報に大きく影響される一方で、最終的な購買はリアル店舗で行われるケースが多いのもです。
こうした顧客行動の変化に対応するためには、店舗内外を横断して売上までのファネル一覧の行ータを分析する視点が不可欠です。
属人的なVMD・販促からの脱却
従来の「勘と経験に頼った売場づくり」では、成功要因の再現が難しいという課題がありました。データに基づく仮説検証を行うことで、VMD変更の効果を定量的に測定し、感性を数字をもとに改善が可能になります。
アパレルデータ分析の実践ステップ
では、こうしたデータ分析は、どのように進めればよいのでしょうか。アパレル店舗でのデータ分析は、次の3ステップで進めるのが一般的です。
可視化(Visualization):来店数・滞留時間・入店率などをAIカメラサービスなどで取得し可視化
分析(Analysis):時間帯・商品・エリア別など多角的に傾向を把握し、課題を特定
改善(Action):課題に対する打ち手として、VMD・スタッフ配置・販促施策の最適化を実行
このプロセスを繰り返すことで、店舗運営が“感覚”から“データサイクル”へと移行します。 現場スタッフも、データを根拠に意見を出せるようになり、「分析文化」がチームに定着します。
代表的な分析手法
実践ステップについて紹介しましたが、実際にこれを進めるうえでは、データの可視化で歩みが止まってしまうケースも少なくありません。データは用意できたがどう分析すればいいのかわからない、結果をもとに意思決定を行うことが難しい……、そんな事態に陥らないよう、ここからは、店舗現場での改善サイクルを推し進めるのに有効な代表的な分析手法について紹介します。
クラスター分析
手法解説
クラスター分析とは、「性別・年齢」など決め打ちの分類ではなく、顧客・動線・売場行動などから自然に浮かび上がる群(クラスター)を機械的・統計的に分ける手法です。例えば「立ち止まり→手に取る→戻る」動きをする来店客グループ、「入店から速やかに購入に至る」グループ、など複数に分け、それぞれに共通する特徴を明らかにします。
具体に何ができるか
店舗内で「立ち止まり後、買上げに至らない」クラスターを抽出し、その行動パターンから売場レイアウトやPOPの改善ポイントを洗い出せます。
「試着→購入」のスムーズな行動を取るクラスターを特定し、その動線を他のゾーンへ展開することで、売上アップに向けた売場設計を高速で回せます。
複数店舗を比較し、「同じ商品の異なるクラスター構成」を見ることで、店舗ごとの改善テーマを明確化できます。
トレンド分析
手法解説
トレンド分析は「時間的な変化」に注目してデータを分析する手法です。売上・在庫・立ち止まり数などのKPIを時系列で把握し、「いつ」「どこで」「どう変わったか」を捉えて、変化の原因を探ります。
具体に何ができるか
例えば「立ち止まり数は4~6時台に高いのに、購買率が低い」という時間帯を特定し、その時間の接客強化やポップ提示を即時施策化できます。
週や月ごとに「棚前滞留→購入化率」の推移を分析し、VMD変更/什器移動の効果を迅速に検証し、次の施策へ反映できます。
店舗全体/カテゴリ別で「ピーク時間の変化」を捉え、新たな来店動向に合わせた売場レイアウト変更や人員シフトの見直しを高速で進められます。
クロス分析
手法解説
クロス分析(クロス集計)は、2〜3の条件(例えば「性別=女性」「年齢=30代」「来店時間=午後」)に当てはまる集団を抽出し、その集団内の行動・購入傾向を分析する手法です。
具体に何ができるか
「午後の30代女性で立ち止まりは多いが購入に至っていない」層を抽出し、その層専用の訴求(色・素材・接客トーン)を検討できます。
買上げ頻度が高い「頻来店客×サイズS」で、立ち止まり→商品手に取り率が高いかどうかを見て、人気什器位置の移動やPOP訴求を最適化できます。
複数要素(来店方法・曜日・時間帯)を重ねて分析し、売場改善の施策対象を明確にして、無駄な改善リソースを削減できます。
実践事例──LOVELLESSに見るデータ活用の成果
三陽商会のセレクトショップ「LOVELLESS」店舗スタッフの感性とデータを融合した売場づくりを実践しています。
AIカメラによる来店分析から得られるデータをもとに、顧客がどのエリアに滞留しているか、どの商品に関心を示しているかを把握。これらの情報をもとにブランド体験を再設計し、“感覚を再現可能な知見”へと変換しています。
これにより、VMD改善やスタッフ動線の最適化など、現場レベルでの効果が現れています。
データ分析を“文化”として根付かせるために
データ分析の効果を持続させるには、ツールを導入しデータを可視化するだけではなく、データを読む・共有する・改善につなげる仕組みを整えることが重要です。
定期的なKPIレビューを実施し、分析を「業務プロセスの一部」に組み込む
現場スタッフが“自分たちで数字を語る”環境をつくる
成功事例を社内で共有し、横展開していく
このように、データ分析を“特別な業務”ではなく“日常の習慣”に変えていくことが、成果を生み出すための第一歩です。
感性とデータが共存するアパレル運営へ
最後に覚えておいてほしいことは、アパレルにおけるデータ分析は、“感性を否定する”ものではないということです。むしろ、データ分析とは、感性を科学的に理解し、再現性を高めるための手段だといえます。
データがスタッフ間の共通言語となることで、属人的な判断を超えたチーム運営が実現します。そして、ブランド体験の質を高めながら、持続的な改善を生み出す。その中心にあるのが、アパレルデータ分析という文化です。
※ABEJA Insight for Retail の導入成功事例
ABEJA Insight for Retailのご紹介
ABEJAでは小売店舗向けのストアアナリティクスを提供しております。現在、600店舗以上で導入されており、分析精度の高さとデータ分析サポート体制において高い評価をいただいております。
少しでもご興味を持っていただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼サービス詳細はこちら
https://abejainc.com/insight-retail-main
▼お問い合わせはこちら















